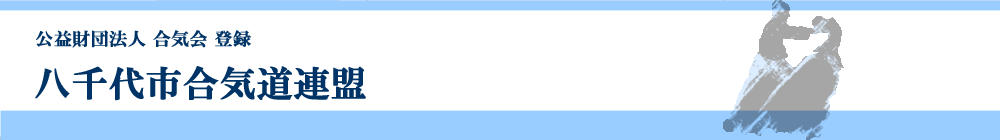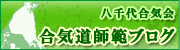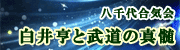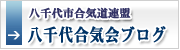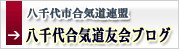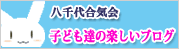合気道初心者に役立つ、知っておくと良い合気道関連用語の解説をします。
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 合気神社 | あいきじんじゃ | 戦争を終わらせるために茨城県笠間市(旧岩間町)に建てられた神社、43柱の神々が祭られていて、4月29日に例大祭が行われる |
| 合気道着(道着) | あいきどうぎ(どうぎ) | 柔道着を合気道に合うように改良したもの |
| 合気道本部道場 | あいきどうほんぶどうじょう | 新宿区若松町にある公益財団法人 合気会の本部道場、合気会の会員は誰でも稽古に参加できる(有料) |
| 相半身 | あいはんみ | 相手と同じ側の手足を前に出す半身の構え |
| 当身 | あてみ | 人体の急所を打撃することだが、合気道は気当てにより、直接人体に当てない当身が多い |
| 合わせ | あわせ | 結び |
| 一教 | いっきょう | 第一教を略して一教と呼ぶことが多い |
| 一教運動 | いっきょううんどう | 一教の動きを単独動作で行うもの |
| 入身 | いりみ | 相手の攻撃線を外して、相手の側面又は裏まで入る体捌き |
| 入身投げ | いりみなげ | 入身の体捌きを用いて相手を投げる技 |
| 植芝吉祥丸 | うえしば きっしょうまる | 二代目道主 |
| 植芝守央 | うえしば もりてる | 三代目道主 |
| 植芝盛平 | うえしば もりへい | 合気道開祖、初代道主 |
| 受け | うけ | 攻撃側で、技を掛けられて受身を取る人 |
| 受身 | うけみ | 投げられた時にけがをしないようにするための方法 |
| 後取り | うしろどり | 受けが取りの後ろから攻撃する取り方 |
| 裏 | うら | 相手の後ろ側面又は背面 |
| 襟取り | えりどり | 襟を掴む取り方、前襟取りと後襟取りがある |
| 演武 | えんぶ | 公開の目的などで合気道の技を見せること |
| 翁先生、大先生 | おうせんせい、おおせんせい | 開祖の尊称、生前は翁先生、入神後は大先生 |
| 大本教 | おおもときょう | 開祖が帰依した神道の宗派、最大時で信徒数800万人、開祖は出口王仁三郎聖師から影響を受けた |
| 応用技 | おうようわざ | 基本技以外の取り方で攻撃されたときに取りが基本技と同じ技を施す、その技のこと(基本技の正面打ち入身投げに対して横面打ち入身投げは応用技) |
| 表 | おもて | 相手の前面 |
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 回転投げ | かいてんなげ | 相手の後頭部を押さえて、片手を矢筈の手で取って投げる技 |
| 返し技 | かえしわざ | 取りが施す技を返して、受けが反撃する技 |
| 懸かり稽古 | かかりげいこ | 一人の取りに、次々と受け変わって懸かって行く稽古法 |
| 片手取り | かたてどり | 取りの右(左)手を左(右)手で掴む取り方 |
| 肩取り | かたどり | 肩を掴む取り方 |
| 固め技 | かためわざ | 関節技で極める技 |
| 合蹠運動 | がっせきうんどう | 足の裏を付けて膝を上下に動かす運動 |
| 構え | かまえ | 半身の構え |
| 関節技 | かんせつわざ | 関節を極めて相手を生け捕りにする技、固め技 |
| 気 | き | 宇宙に充満しているエネルギーと人間が倒れないように保っているものがある |
| 跪座 | きざ | 爪先を立てて座ること |
| 基本技 | きほんわざ | 技のうちで一番簡単で、技の理合が含まれているもの |
| 逆半身 | ぎゃくはんみ | 相手と反対側の手足を前に出す半身の構え |
| 交差取り | こうさどり | 取りの右(左)手を右(左)手で掴む取り方 |
| 呼吸投げ | こきゅうなげ | 特別な名称が付いていない技の総称、呼吸力を遣った技 |
| 呼吸法 | こきゅうほう | 呼吸力の養成法ともいわれるが呼吸力の遣い方を学ぶ方法、立技と座技がある |
| 呼吸力 | こきゅうりょく | 気の力、イメージ(念)の力、呼吸によって気を吸収することにより強められる |
| 五教 | ごきょう | 第五教を略して五教と呼ぶことが多い |
| 腰投げ | こしなげ | 相手を腰に乗せて投げる技 |
| 小手返し | こてがえし | 手首、肘、肩の関節を極めて投げる技 |
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 坐技 | ざぎ(又は すわりわざ) | 座技 |
| 捌き | さばき | 体捌き(足捌き)のことをいうことが多い |
| 残心 | ざんしん | 投げた後、相手の反撃に注意する心構えと反撃にただちに対応できる身構えのこと |
| 三教 | さんきょう | 第三教を略して三教と呼ぶことが多い |
| 三人掛け | さんにんがけ | 三人の受けを相手に行う自由取り |
| 膝行 | しっこう | 座っているときの歩み方 |
| 四方投げ | しほうなげ | 四方八方に投げる技 |
| 自由取り | じゆうどり | 施す技を決めないで臨機応変に技を施すやり方 |
| 十字絡み | じゅうじがらみ | 肘関節を極めて投げる技 |
| 杖取り | じょうどり | 武器取りの一つで杖を相手にするもの |
| 正面打ち | しょうめんうち | 取りの面を打つ攻撃方法 |
| 隅落し | すみおとし | 受けの斜め後ろに導いて投げる技 |
| 座技 | すわりわざ(又は ざぎ) | お互いに座って行う技、坐技 |
| 臍下丹田 | せいかたんでん | 臍の下10 cm位の所、下丹田、中心 |
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 第一教 | だいいっきょう | 腕押え |
| 第五教 | だいごきょう | 腕伸し(九字抑え)、短刀取りに遣う |
| 体捌き | たいさばき | 入身、転換、転身の足捌き |
| 第三教 | だいさんきょう | 小手捻り |
| 第二教 | だいにきょう | 小手回し |
| 第四教 | だいよんきょう | 手首抑え |
| 武産 | たけむす | 結びによって無限に技が生まれる様 |
| 太刀取り | たちどり | 武器取りの一つで剣を相手にするもの |
| 立技 | たちわざ | お互いに立って行う技 |
| 多人数掛け | たにんずうがけ | 四人以上の受けを相手に行う自由取り |
| 短刀取り | たんとうどり | 武器取りの一つで短刀を相手にするもの |
| 転換 | てんかん | 自分の背中の方に足を引いて回る捌き |
| 転身 | てんしん | 右足と左足を踏み変えて身を入れ替える |
| 天地投げ | てんちなげ | 受けの気を天地に分けて投げる技 |
| 天秤投げ | てんびんなげ | 現在は呼吸投げの一つになっている |
| 取り | とり | 受けに技を掛ける人 |
| 鳥船の行 | とりふねのぎょう | 船漕ぎ運動ともいい、気を強める禊法 |
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 投げ技 | なげわざ | 取りが受けを投げる技 |
| 二教 | にきょう | 第二教を略して二教と呼ぶことが多い |
| 二人掛け | ににんがけ | 二人の受けを相手に行う自由取り |
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 背伸運動 | はいしんうんどう | クールダウンのために相手を仰向けにして背中に乗せて伸ばす運動 |
| 半身 | はんみ | 片方の手と足を前に出す構え |
| 半身半立ち技 | はんみはんだちわざ | 座っている取りに対して受けが立って攻撃するときの技 |
| 肘固め | ひじがため | 相手の肘を極める固め技、脇固めともいう |
| 肘取り | ひじどり | 取りのどちらかの肘を掴む取り方 |
| 左半身 | ひだりはんみ | 左手左足を前に出す構え |
| 振魂の行 | ふりたまのぎょう | 左手を上にして両手を十字に組んで臍の所で動かす神道の行で、気を強める禊法 |
| 変化技 | へんかわざ | 同じ取り方・攻撃法に対して、ある技を施そうとして不具合が生じたとき等に技を変えて対処する、その技のこと(技の進展により適切な技に切り替えること) |
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 間合い | まあい | 相手との距離、肉体的な間合いと精神的な間合いとがある |
| 右半身 | みぎはんみ | 右手右足を前に出す構え |
| 結び(産霊) | むすび(むすび) | 気と気が融合すること |
| 胸取り | むなどり | 取りの胸を片手で掴む取り方 |
| 目付け | めつけ | 相手を見つめないで、相手全体を目に映すように見ること |
| 諸手取り | もろてどり | 取りの片手を両手で掴む取り方 |
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 矢筈の手 | やはずのて | 相手の手を親指と人差し指の間に挟むようにする手の形 |
| 横面打ち | よこめんうち | 取りの横面(こめかみ、耳)や頚動脈を打つ攻撃方法 |
| 四教 | よんきょう | 第四教を略して四教と呼ぶことが多い |
| 用 語 | 読 み | 解 説 |
|---|---|---|
| 両肩取り | りょうかたどり | 取りの両肩を掴む取り方 |
| 両手取り | りょうてどり | 取りの両手を掴む取り方 |